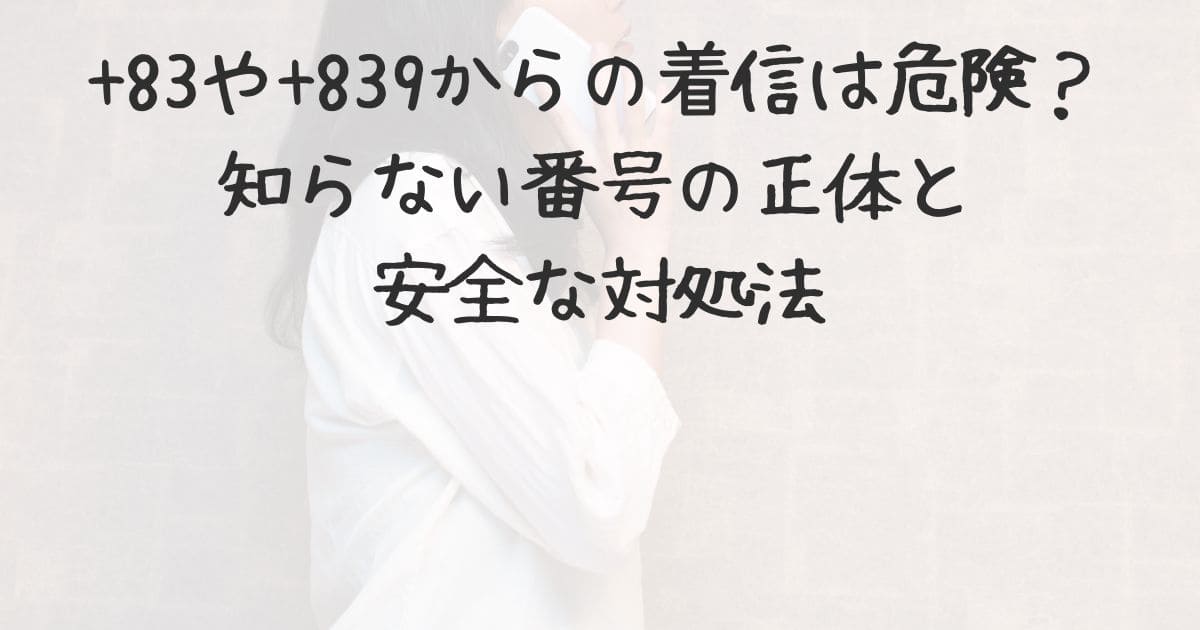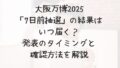最近、スマホに「+83」や「+839」といった聞き慣れない番号から着信が増えているという声が多く寄せられています。
「どこの国から?」「折り返したほうがいいの?」と不安に思う方も少なくありません。
しかし実は、この番号は正式な国番号ではなく、詐欺や迷惑電話に悪用されている可能性が高いのです。
本記事では、+83からの着信の正体、なぜ存在しない番号が表示されるのか、その裏に潜む危険性をわかりやすく解説します。
さらに「絶対にやってはいけない行動」や「安全なブロック方法」、もし被害に遭ってしまったときの相談先まで、具体的な対処法をまとめました。
不審な国際電話に惑わされないために、この記事を読んで冷静な判断力を身につけましょう。
+83からの着信は危険?知らない番号の正体とは

見慣れない「+83」や「+839」といった国際番号から電話がかかってくると、思わず不安になってしまいますよね。
ここでは、そもそも国際電話番号とは何か、そしてなぜ存在しないはずの+83から着信が届くのかを解説します。
国際電話番号の基本ルールと+83の位置づけ
国際電話をかけるときには「+」に続けて国番号が付きます。
例えば日本なら「+81」、アメリカやカナダなら「+1」が正式な国番号です。
この国番号は、国際電気通信連合(ITU)が管理しており、公式のリストに登録されています。
しかし「+83」や「+839」は、そのリストには存在しません。
つまり、正式な国番号ではないのに着信がある時点で不自然だということです。
| 国名 | 国番号 |
|---|---|
| 日本 | +81 |
| アメリカ/カナダ | +1 |
| 中国 | +86 |
| 存在しない番号 | +83, +839 |
なぜ存在しない番号から着信があるのか?
存在しない番号から着信があるのは「スプーフィング」と呼ばれる技術が悪用されているからです。
スプーフィングとは、発信者の電話番号を偽装して、受信者をだます手法のことを指します。
もともとは「050」などのIP電話番号がよく使われていましたが、規制が厳しくなり、近年は国際番号を偽装するケースが増えてきました。
特に国際番号は国内での遮断が難しいため、詐欺グループに悪用されやすいのです。
| スプーフィングの特徴 | 被害例 |
|---|---|
| 存在しない番号を使う | +83や+839からの着信 |
| 不安をあおる音声を流す | 「入国管理局からの通知」など |
| 折り返しを誘導する | ワン切りで高額料金を狙う |
+83や+839の着信が怪しい理由

では、なぜ+83や+839からの着信が「怪しい」とされるのでしょうか。
ここでは、その背後にある具体的な手口や、実際に報告されている事例を紹介します。
スプーフィング(番号偽装)の仕組み
スプーフィングの目的は「正体を隠して相手をだます」ことにあります。
たとえば電話を受けた人に「国際的な機関からの連絡かもしれない」と思わせれば、冷静な判断を鈍らせることができます。
その結果、折り返し通話や個人情報の提供といった行動を引き出すのです。
つまり、番号の表示は信用できないということを前提に考える必要があります。
| 手口 | 狙い |
|---|---|
| ワン切り | 折り返させて高額料金を発生させる |
| 自動音声 | 「入国管理局」など不安をあおる |
| SMS連動 | 不審なURLを踏ませる |
実際に報告されている怪しい着信の事例
ネット上では、+83や+839からの着信についてさまざまな報告が上がっています。
中でも多いのは、中国語や英語の自動音声が流れるケースです。
内容は「入国管理局からの通知」や「大使館からのお知らせ」といったものが多く、受信者を動揺させることを狙っています。
このような電話は、ほぼ間違いなく詐欺や迷惑目的のものです。
| 報告されている内容 | 想定される目的 |
|---|---|
| 中国語の自動音声 | 中国系住民を対象にした詐欺 |
| 「未払い料金があります」 | 架空請求 |
| 「大使館からのお知らせ」 | 不安をあおって金銭を要求 |
不審な+83からの着信にどう対応すべき?

見知らぬ+83や+839からの電話がかかってきたとき、慌てて対応してしまうと被害につながる可能性があります。
ここでは、やってはいけない行動と、安全な対処法を整理します。
絶対にやってはいけない行動
一番避けるべきは、電話に出たり折り返しをかけたりすることです。
特にワン切りで折り返しを誘うケースは、高額な通話料を請求される可能性があります。
気になっても絶対に発信してはいけません。
また、電話に出てしまった場合でも、名前や住所、口座番号といった個人情報を話すのは厳禁です。
少しでも不審に思ったら、即座に通話を切ることが最大の防御です。
| NG行動 | リスク |
|---|---|
| 折り返し電話をする | 高額請求の可能性 |
| 個人情報を話す | 詐欺に悪用される |
| 指示に従って送金する | 金銭被害 |
安全に着信を無視・ブロックする方法
不審な番号からの着信には、そもそも出ないのが最も効果的です。
さらに、スマホの設定やアプリを利用すれば、着信自体をブロックできます。
たとえばiPhoneやAndroidには、迷惑電話を警告・拒否する機能があります。
また、専用のアプリを導入すると、より高精度で迷惑電話を判定してくれます。
海外とのやり取りが不要な人は、携帯会社のサービスで国際電話をブロックしておくのもおすすめです。
| 対策方法 | 効果 |
|---|---|
| スマホ標準の迷惑電話設定 | 基本的な警告や拒否が可能 |
| 専用アプリの導入 | 迷惑番号データベースを活用して自動判定 |
| キャリアの国際電話ブロック | 海外からの不要な着信を根本的に防ぐ |
もし+83からの電話で詐欺に巻き込まれたら

注意していても、うっかり応答してしまったり、怪しい指示に従ってしまうケースもあります。
そんなときは、被害を最小限にするための冷静な対応が欠かせません。
被害に遭ったときの初期対応
万が一金銭を送ってしまった場合や、個人情報を伝えてしまった場合は、すぐに行動を起こしましょう。
まずは銀行やクレジットカード会社に連絡し、不正利用を防止する手続きを依頼します。
さらに、スマホのSMSやメールに怪しいメッセージが届いた場合は、開かず削除することが重要です。
「自分は大丈夫」と思って油断せず、少しでも不安があれば早めに相談してください。
| 状況 | 対応方法 |
|---|---|
| 金銭を送ってしまった | 銀行やカード会社へ連絡 |
| 個人情報を伝えてしまった | パスワード変更や利用停止手続き |
| 怪しいSMSやメールを受信 | 無視して削除 |
警察や消費者ホットラインなど相談窓口の活用
詐欺の疑いがある場合は、ひとりで悩まずに相談窓口を利用しましょう。
警察の「#9110」や、消費生活センターの「188(いやや)」が代表的な相談先です。
また、専門家に相談したいときは「法テラス」で無料相談を受けられるケースもあります。
被害を受けたことを恥ずかしがる必要はありません。
むしろ早めに声をあげることで、同じ被害に遭う人を減らすことにつながります。
| 相談窓口 | 電話番号 |
|---|---|
| 警察相談専用ダイヤル | #9110 |
| 消費者ホットライン | 188 |
| 法テラス | 0570-078374 |
スマホでできる迷惑電話対策

+83や+839からの不審な着信を防ぐには、スマホ自体の機能やサービスをうまく活用することが大切です。
ここでは、すぐに実践できる迷惑電話対策を紹介します。
キャリアの国際電話ブロックサービス
携帯キャリア各社では、国際電話の発着信を制限できるサービスを提供しています。
海外とやり取りをしない人であれば、この機能を利用するだけで多くの迷惑電話を防ぐことができます。
特にワン切り型の国際詐欺は、ブロック設定で根本的に防げるケースが多いです。
設定方法はキャリアによって異なりますが、公式サイトやサポート窓口から簡単に申し込めます。
| キャリア | 提供サービス |
|---|---|
| NTTドコモ | 国際電話停止サービス |
| au | 国際電話発着信制限 |
| ソフトバンク | 国際電話発着信制限 |
迷惑電話アプリの活用方法
スマホにインストールできる迷惑電話対策アプリも効果的です。
アプリは膨大な迷惑番号のデータベースを参照し、自動的に警告を出したり、着信をブロックしてくれます。
自分で番号を調べる手間が省けるので、日常的な安心感が高まります。
代表的なアプリには「Whoscall」や「Truecaller」などがあります。
これらは口コミ情報とも連動しているため、新しい手口にも対応しやすいのがメリットです。
| アプリ名 | 特徴 |
|---|---|
| Whoscall | 世界規模のデータベースで番号を判定 |
| Truecaller | 不審な番号を自動でブロック |
| 電話帳ナビ | 国内利用者の口コミと連動 |
まとめ|+83着信に惑わされないために
ここまで、+83や+839からの不審な着信について、その正体や危険性、対策方法を見てきました。
最後に、大切なポイントを整理します。
日常で心がけるべき3つのポイント
1. 不審な番号には出ない・折り返さない
最も基本的で効果的な防御策です。
2. スマホの機能やサービスを活用する
国際電話ブロックや迷惑電話アプリを導入しておくと安心です。
3. 被害に遭ったら早めに相談する
警察や消費者ホットラインに連絡し、被害拡大を防ぎましょう。
| やるべきこと | 効果 |
|---|---|
| 不審な番号に出ない | トラブル回避 |
| スマホやキャリアの機能を使う | 自動的にブロックできる |
| 被害時は早めに相談 | 被害を最小限に抑える |
冷静な判断が自分を守る
見知らぬ国際番号からの着信は、不安をあおるように仕組まれているケースがほとんどです。
しかし、冷静に対応すれば被害を防ぐことができます。
「出ない・折り返さない・相談する」というシンプルなルールを守ることが、最も確実な対策です。
日常的に注意を払い、自分と大切な人を守る行動を心がけましょう。