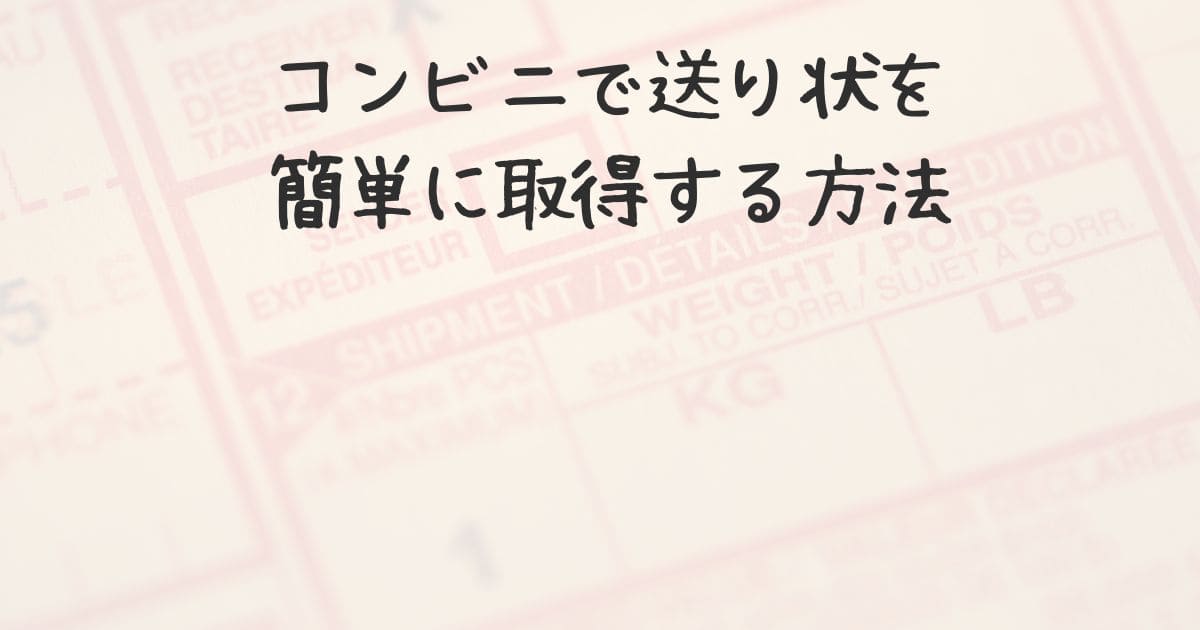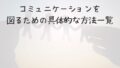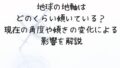荷物を送るときに必要な「送り状(伝票)」ですが、「送り状だけもらいたい」「コンビニで簡単に手に入れたい」と思ったことはありませんか?
本記事では、主要なコンビニ(ローソン・セブン-イレブン・ファミリーマート)で送り状を入手する具体的な方法や注意点を、初心者にもわかりやすく解説しています。
さらに、送り状の種類やスマホアプリとの連携、梱包のコツ、集荷の使い方まで幅広くカバー。
これから荷物を送る方にとって、役立つ情報が満載です。
コンビニで送り状をもらう方法

送り状はどこにある?
コンビニに設置された専用端末やレジカウンター付近に、各配送会社の送り状が置かれていることが多く、気軽に手に取ることができます。
送り状は、ローソンやセブン-イレブン、ファミリーマートなど、それぞれのコンビニが提携している配送会社によって種類が異なります。
例えば、ヤマト運輸ならクロネコヤマト、郵便局系ならゆうパック、佐川急便など、店舗ごとに対応状況が違うため、訪問前に事前確認することが安心です。
また、店員に直接「送り状ありますか?」と尋ねると、必要な場所を教えてくれる場合も多いです。
必要なサイズと種類について
送り状には「宅急便」「クール便」「着払い」「代金引換」「ネコポス」など、多彩な種類が用意されています。
これらは荷物の大きさや重さ、送る内容に応じて使い分ける必要があります。
たとえば、生鮮食品には冷蔵保存が可能なクール便、小型の書類や商品にはネコポスなどが便利です。
どの送り状が適しているか迷った場合は、端末の案内や店員に確認するのがおすすめです。
受取方法と流れを理解する
送り状の受け取り方法としては、店頭の端末(Loppiやマルチコピー機、Famiポートなど)を利用し、画面に従って配送会社や送り状の種類を選択します。
必要な情報を入力後、レシートや受付票が発行されるので、それを持ってレジに行くと送り状がもらえる仕組みです。
中にはスマホと連携してQRコードを使った発行方式もあるため、事前にアプリで準備しておくと手続きがよりスムーズになります。
主要コンビニの送り状取得方法

ローソンでの手続き
ローソンではLoppi端末を使って送り状を発行できます。
- 画面上で「宅配便」メニューを選び、配送会社(ヤマト運輸やゆうパック)と送り状の種類を指定します。
- その後、必要事項を入力してレシートを発行し、それをレジへ持参すれば送り状が受け取れます。
店頭で印刷された伝票はそのまま荷物に貼付できる形式になっており、手間がかかりません。
Loppiの操作は初めてでも案内がわかりやすく、店員がサポートしてくれるので安心です。
セブン-イレブンでの手続き
セブン-イレブンではマルチコピー機を活用して送り状を発行します。
スマホであらかじめ作成した送り状のQRコードや受付番号を入力すれば、印刷が開始されます。
印刷された伝票はレジに持っていき、正式な送り状と交換するか、すぐに発送手続きが可能です。
マルチコピー機は簡単なタッチ操作で進められ、短時間で手続きが完了します。
ファミリーマートでの手続き
ファミリーマートではFamiポート端末を使ってヤマト運輸の送り状を発行できます。
画面から宅配便メニューを選択し、必要事項を入力後にレシートが発行され、それをレジに提示すると用紙タイプの送り状がもらえます。
さらに、スマホアプリと連携して、QRコードを読み取るだけで発行手続きが完了する方法もあります。
手軽に利用できるため、初めての方でも簡単に操作できます。
送り状の種類と特徴

ヤマト運輸の送り状
伝票には元払い、着払い、ネコポス、宅急便コンパクトなどがあります。
オンライン連携も可能です。
ゆうパックの送り状
郵便局と同様の取り扱いが可能で、持込割引やゆうプリタッチとの連携があります。
佐川急便の送り状
一部コンビニでは非対応。必要な場合は公式サイトでの事前発行か、対応店舗の確認が必須です。
送り状をもらう際の注意点

必要な情報を記入するポイント
宛名・住所・電話番号・品名などは正確に記入しましょう。
文字の誤りや書き損じは配送トラブルの原因となり、配達先が特定できない場合は返送されたり、場合によっては紛失扱いとなってしまうこともあります。
特に品名は、内容物の確認や補償対象の判断材料にもなるため、具体的でわかりやすい記述を心がけると良いでしょう。
また、荷物の取り違えや誤配送を防ぐためにも、記入後には必ず一度見直しを行うことをおすすめします。
店員に確認する際の質問例
「この荷物に合う送り状はどれですか?」「スマホで作った送り状はここで使えますか?」「この伝票は店頭印刷できますか?」など、疑問があれば遠慮せずに店員に尋ねるようにしましょう。
送り状の種類によっては、店舗によって対応できないケースや、特定の端末でしか発行できない場合もあります。
事前に確認しておけば、無駄足を避けることができます。
受付時間と店舗の取扱い
一部のコンビニでは、深夜や早朝などの時間帯に宅配受付を行っていない場合があります。
これは、スタッフの人数やレジの混雑具合、配送会社との契約条件などによるものです。
また、同じチェーンでも店舗によって取り扱い可能な配送業者が異なることもあるため、「この店舗でヤマト運輸の受付は可能ですか?」などと確認しておくと安心です。
事前準備と便利なツール

スマホアプリで事前登録
ヤマト運輸や日本郵便のアプリを使えば、送り状の作成がスマホだけで完結し、QRコードを表示させることで、対応コンビニの端末から簡単に印刷することが可能です。
アプリでは、宛名・差出人情報・品名などを事前入力できるため、店頭での手間が大幅に軽減されます。
さらに、配送履歴の管理や荷物の追跡機能も備わっており、送り状の管理が一元化できて便利です。
忙しい方や頻繁に発送を行う人にとっては、効率的な発送手段として非常に有効です。
Loppiの利用方法
ローソン店内に設置されたLoppi端末では、「宅配便」メニューから送り状の発行を行います。
画面に従って配送方法や荷物情報、届け先を入力するだけでレシートが出力され、それをレジに持っていけば専用の送り状が発行されます。
Loppiは画面が分かりやすく、初めて使う方でも安心して操作できる設計です。
また、スマホで事前に入力した情報を反映できるサービスもあるため、時間短縮にも役立ちます。
印刷可能な伝票のダウンロード
配送会社の公式サイトを利用すれば、自宅のプリンターで送り状を印刷することも可能です。
オンラインで送り状情報を入力した後にPDF形式で保存・印刷すれば、そのまま荷物に貼って持ち込むことができます。
特に業務用途や自宅にプリンター環境がある方には最適な方法です。
フォーマットによっては切り取り線や貼付欄があるため、丁寧に扱うことでトラブル防止につながります。
ダンボール箱の選び方

サイズの測り方と目安
縦・横・高さの合計でサイズを判断します。
一般的に、配送会社ではこの3辺の合計が60cm・80cm・100cmなどの区分で料金が設定されているため、少しでもサイズを抑えることが送料節約につながります。
特に宅配便コンパクトなどの定額制サービスを活用すると、コストパフォーマンスが良くなるためおすすめです。
荷物のサイズを測る際は、柔らかいメジャーや巻き尺を使うと正確に測ることができます。
環境に配慮した梱包方法
再利用可能なダンボールや緩衝材(新聞紙・エアパッキン・古布など)を使用すれば、エコで安全な発送が可能です。
梱包材を購入する代わりに、家にある資源を上手に使うことでコスト削減にもつながります。
また、不要になったダンボール箱を再利用する場合は、以前の送り状やバーコードが残っていないかを確認し、しっかりはがしてから使用しましょう。
環境への配慮と配送トラブルの防止、両方の観点から適切な梱包が求められます。
コンパクトに発送するためのテクニック
衣類などの柔らかい物は圧縮袋を使用すると大幅に体積を減らせます。
また、壊れやすい物でも無駄なスペースが少なければ、箱の中で動かず破損リスクも軽減されます。
段ボールに荷物を詰める際は、すき間を緩衝材でしっかり埋めることで、中身が固定され安全に運ばれます。
特に小さな荷物を送る際は、袋型パッケージを利用するとコンパクトに収まり、サイズ制限をクリアしやすくなります。
集荷サービスの利用方法

自宅での集荷手続き
配送会社の公式サイトやアプリから集荷依頼を行えます。希望日時の選択が可能です。
指定日時に集荷を依頼する
忙しい方に便利なオプション。時間を指定することで在宅時に確実に荷物を渡せます。
集荷料金の確認ポイント
通常配送料とは別に集荷料金が加算される場合があるので、事前に確認しておきましょう。
手続き完了後の流れ

控えの保管方法
送り状の控えは、トラブル対応や追跡に必要なため、必ず保管しておきましょう。
控えには送り状番号が記載されており、荷物の紛失や遅延が発生した際の問い合わせ時に非常に重要な情報源となります。
また、荷物を送った証明として活用できるため、ビジネス利用や高価な品物の配送時には特に保管が推奨されます。
保管期間は、最低でも配送完了から数週間は保持しておくと安心です。
配達日時の確認方法
配送会社の追跡サービスを利用すれば、配達予定日や現在の配送状況をリアルタイムで確認することができます。
特にWEBやスマホアプリを使うと、荷物が今どこにあるのか、配達までどれくらいかかるのかを即座にチェックできます。
一部の配送会社では、配達予定時間の指定や再配達依頼もオンラインから可能です。
送付先からの受取通知
送り先から「届いたよ」と連絡があると安心できますが、それだけでなく事前に追跡番号を共有しておくと、受け取り側も状況を確認できて便利です。
荷物の到着目安がわかることで、受取人側も在宅準備ができ、スムーズな受け渡しにつながります。
特にビジネスの取引や贈答品などの場合は、受取通知をもらうことで送付完了の証明にもなります。
よくある質問(FAQ)

送り状の再発行はできる?
基本的には再発行不可ですが、控えを持っていれば追跡番号から対応できるケースもあります。
紛失や破損によって送り状の情報がわからなくなってしまった場合でも、控えに記載された番号があれば、配送会社へ問い合わせて状況の確認や必要な対応を進めてもらえることがあります。
発送時には、控えを写真に残したり、クラウドサービスに保管しておくとより安全です。
荷物の追跡方法について
各社の公式サイトやアプリで、送り状番号を入力することで追跡できます。
ヤマト運輸、ゆうパック、佐川急便などは、それぞれ専用の荷物追跡ページやアプリを提供しており、配達状況や現在の配送場所、予定配達日などをリアルタイムで確認することが可能です。
また、配達前通知や再配達の依頼もアプリ内から簡単に行える機能が備わっている場合が多く、利便性が非常に高くなっています。
料金の割引について
スマホ事前登録や持込・集荷割引、複数個割引などを活用しましょう。
たとえば、ヤマト運輸ではスマホで送り状を作成し、持ち込みにすると割引が適用される「デジタル割」があります。
日本郵便もゆうプリタッチやゆうパックWeb割を利用することで送料を抑えられます。
法人利用やフリマ発送を頻繁に行う方は、契約割引や提携サービスの特典を確認しておくとさらにお得です。
まとめ
コンビニで送り状を取得する手順は、一見すると複雑に感じるかもしれませんが、実際は非常にシンプルで便利な仕組みが整っています。
Loppiやマルチコピー機、Famiポートなどの端末を活用すれば、送り状は簡単に手に入り、スマホとの連携で手続きもさらにスムーズになります。
また、適切な梱包やサイズ選び、集荷サービスの利用によって、より効率的に発送を行うことも可能です。
ぜひ本記事を参考に、自分に合った方法で手軽に送り状を入手し、安心・確実な発送を実現してください。