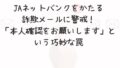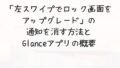「お盆って毎年いつから?」と疑問に思う方は多いでしょう。
結論から言えば、全国的には 8月13日から16日 が一般的なお盆期間とされています。
しかし地域によって少しずつ異なり、東京や横浜の一部では7月13日から16日に行われる「7月盆」、沖縄や奄美では旧暦を採用するため毎年日付が変わる「旧盆」があります。
例えば2025年の旧盆は8月6日から8日です。
旅行や帰省の予定を立てる前に、自分の地域のお盆の日程をきちんと確認しておくことが大切です。これにより準備もスムーズになり、安心してご先祖さまを迎えられます。
お盆の由来と歴史を知って深まる理解

お盆は仏教の教えに基づき、ご先祖さまの霊を迎えて供養する大切な行事です。
起源は中国からの仏教行事「盂蘭盆会」にさかのぼり、日本では先祖崇拝の風習と融合し、独自の文化へと発展しました。
時代とともに地域ごとにさまざまな習慣が生まれ、現在の多様なお盆の形が形成されています。
歴史を知ることで、供養に込められた意味がより深く理解でき、気持ちも一層込めやすくなります。
地域による違い:7月盆・8月盆・旧盆(旧暦)

お盆は全国一律ではなく、土地ごとに違いがあります。
東京や神奈川の一部では7月盆を採用しており、北海道や東北、九州などでは8月盆が主流です。
一方、沖縄や奄美群島などでは旧暦をもとにした旧盆が今も大切に守られています。
このため日程は毎年変わります。地域ごとの風習を知っておくと、旅行先や親戚宅でも適切な対応ができ、安心して過ごせます。
用語整理:「盆入り」「中日」「盆明け」とは

- 盆入り:ご先祖さまを迎える13日。この日には家の玄関や仏壇を整え、迎え火を焚く準備をする家庭が多いです。提灯を灯して霊が迷わず帰れるようにする意味もあります。
- 中日:14日・15日、ご先祖さまと過ごす大切な期間。家族で集まり食事を共にし、仏壇にお供えをして感謝を伝える日です。地域によっては親戚が集まり、法要や盆踊りが行われ賑わいます。
- 盆明け:16日、送り火を焚きご先祖さまをお見送りする日。送り火には「安全にあの世へお帰りください」という願いが込められています。各地では精霊流しや花火大会が開かれることもあり、独特の情緒を楽しめます。 地域によっては、盆踊りや提灯流しなども加わり、お盆特有の華やかな雰囲気を体感できます。昔ながらの習慣と現代的な楽しみが混ざり合い、多くの人の心に残る時間となります。
お供え物・飾りの意味と選び方

お盆には精霊棚(盆棚)を飾り、ご先祖さまが安心して過ごせる空間を整えます。
ナスやキュウリで作った精霊馬・精霊牛には「早く帰ってきて、ゆっくり戻ってください」という願いが込められています。
飾り付けにはほかにも提灯やお花、団子などが用いられ、地域により種類や意味が異なります。
現代では洋花やフルーツ、お菓子を添える家庭も多く、好みや状況に合わせて自由に選ばれています。大切なのは形式よりも気持ち。
心を込めて準備したお供え物は、ご先祖さまにきっと届くでしょう。
お墓参り・迎え火・送り火はいつが良い?

お墓参りは盆入りの13日か中日の14日・15日が目安とされていますが、地域や家ごとの慣習によって異なる場合もあります。
できれば午前中の涼しい時間帯に行くと落ち着いてお参りできます。
迎え火は13日の夕方に玄関先や庭で行い、提灯やろうそくを使ってご先祖さまが迷わず帰れるようにします。
送り火は16日に焚き、名残を惜しみつつ安全にお見送りする気持ちを込めましょう。
雨や予定が合わない場合でも、日をずらして心を込めて手を合わせれば十分です。
お参りの際はお花やお線香、お供えを整えて、感謝の言葉を伝えるとより丁寧な供養になります。
準備はいつから?直前で慌てないためのスケジュール

- 1週間前:家や仏壇、お墓の掃除を済ませ、必要な供物や提灯を確認しておく
- 3日前:盆飾り・お供えを用意し、足りないものがないか再確認。時間があれば仏具も磨きましょう
- 当日:迎え火を焚き、ご先祖さまをお迎え。家族で集まり、静かにお祈りします 忙しい方は最低限「掃除・お花・お供え」だけでも十分ですが、余裕があれば少しずつ準備しておくと安心です。
初盆(新盆)はいつから?何が違う?

初盆は、故人が亡くなってから初めて迎える特別なお盆です。
白提灯を飾って霊を迎える準備を整え、親戚が集まって法要を行うなど一般のお盆より丁寧な供養がされます。
地域によっては僧侶を招いて読経することもあり、より厳かな雰囲気になります。
参列する際は服装を喪服または落ち着いた服装にし、お香典の金額や渡し方のマナーも確認しておきましょう。
会社や学校の「お盆休み」はいつから?

企業のお盆休みは8月13日〜16日を中心に、1週間程度設定されることが多いですが、業種や会社の方針によっては前後に延長されることもあります。
製造業では長期連休を取るケースもあり、サービス業では分散して休みを設定することが多いです。
公共機関や学校は夏休みと重なるため混雑が予想され、特に交通機関や観光地はピーク時に混み合います。
旅行や帰省の計画は早めに立て、渋滞や混雑を避けるために時間帯やルートを工夫すると快適です。早朝や夜間の移動、混雑予想日を外すなどの対策も効果的です。
宗派や家ごとの違いはある?作法はどこまで守るべき?

宗派によって供養の作法やお盆の行い方には細かな違いがあります。
たとえば浄土真宗と曹洞宗では読経や飾りの内容が異なりますが、近年は形式にこだわりすぎず家庭のスタイルに合わせて簡略化する例も増えています。
大切なのは「心を込めて供養する気持ち」であり、無理に慣れない作法を取り入れる必要はありません。
家族で話し合い、地域や家の風習を尊重しつつ、続けやすい形を選ぶと良いでしょう。
忙しい人向け!簡略化しても大丈夫なお盆行事

最低限押さえるべきは「掃除」「お供え」「ご先祖への祈り」です。
時間が取れない場合は迎え火や送り火を小さなろうそくや電気提灯で代用したり、仏壇にお花を飾るだけでも十分な気持ちが伝わります。
短時間でも静かに手を合わせることで、ご先祖さまへの思いはしっかり届きます。
無理のない範囲でできることを取り入れ、気持ちを込めることを優先しましょう。
旅行や帰省とお盆の両立術

渋滞や混雑を避けるなら、早朝移動や平日出発がおすすめです。
さらに、旅行前に交通情報アプリを活用して渋滞ポイントを確認したり、余裕を持ったスケジュールを組むと快適に移動できます。
旅行先でも、宿泊施設や現地の寺院でお線香をあげる、短い時間でも静かに手を合わせると心が落ち着きます。
また、オンラインで法要に参加したり、ビデオ通話で親族と一緒にお祈りをするなど、状況に応じた工夫をすれば、ご先祖さまへの感謝はきちんと伝わります。
持ち運びできるお線香セットを準備しておくと、どこでも供養できて便利です。
SNS時代のお盆の過ごし方

最近はオンライン供養サービスが増え、スマートフォン一つでお盆行事を行えるようになっています。
遠方の親戚と写真や動画を共有しながら思い出を振り返ったり、SNSに感謝のメッセージや供養の様子を投稿して共有する人も増えています。
オンラインアルバムを作成して家族全員で思い出を保存するなど、デジタルを活用することで距離があっても心がつながりやすくなります。
新しい形を取り入れつつ、ご先祖さまを想う気持ちはそのまま大切にしましょう。
子どもと一緒にやってみよう:安全・実感・継承

迎え火や提灯作りを子どもと一緒に体験すると、楽しく伝統を学べます。
小さな子でも飾り付けやお供えの準備に参加でき、自然と文化への興味が湧きます。
火を使うときは必ず大人がそばで見守り、安全な場所を選んで行いましょう。
また、お盆の意味を優しく説明し、家族の思い出やご先祖の話を伝えることで、子どもたちは文化を自然に受け継いでいきます。
体験を通して得た思い出は、家族全員にとってかけがえのない宝物となるでしょう。
よくある質問(Q&A)
- Q:お墓参りはお盆以外でも良い? → もちろん大丈夫です。お盆以外の日に訪れてもご先祖さまは喜んでくださいます。気持ちが大切なので、都合の良いときに手を合わせましょう。
- Q:旧盆の日程はどう決まる? → 旧暦で計算され、毎年日付が変わります。地域ごとに異なるため、事前に確認しておくと安心です。
- Q:迎え火をしないとご先祖は帰れない? → 形式よりも心が大切です。迎え火をしなくても、家族が祈りを込めればご先祖さまはきちんと帰ってきます。
- Q:遠方で行けない場合は? → お線香をあげたり心で祈るだけでも十分です。電話やオンラインで法要に参加するなど、離れていても思いを届ける方法はたくさんあります。
まとめ:あなたの地域の「盆入り」からがスタート
お盆は、ご先祖さまとつながりを感じる大切な時間です。地域や家の風習を尊重しながら、現代に合わせた形で無理なく過ごしましょう。
少しの時間でも心を込めて供養することが、ご先祖さまへの一番の贈り物になります。
お供えや掃除など簡単なことから始め、家族で過ごすひとときを大切にすると、より豊かな時間となるでしょう。